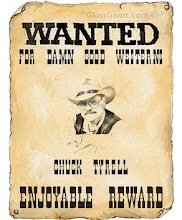バッドランドの決闘
ストンプ・ヘールがRP牧場に着いた時、表情は曇っていたが、目は燃えていた。
「保安官、降りて座らないか」と俺は声を上げた。
ストンプは、がっちりとした身体を起こし、まだら馬から降りながら小さく唸り声を上げた。そして手綱をつなぎ柱に巻いた。「畜生、ネス・ハヴェロック、おまえは本当に遠いところに住みやがって」
俺は「まぶしいから中に入らないか」と言った。「もし望むならコーヒーぐらいはあるだろう」とドアを開けてストンプを中へと招いた。
妻のリタは両手を伸ばして部屋の中央でストンプを迎えた。「アダム・ヘール。お元気でしたか」彼女はストンプの手を取った。「久しぶりにおいでになりましたね。本当にお元気でしたか」ストンプの本名を口にするのはリタだけだ。
ストンプの四角い顔に小さな笑みが浮かんだ。「ハヴェロック夫人、あなたのおいしいコーヒーを飲みに、はるばるセント・ジョーンズから来たのです。本当に」
「それでは、テーブルのところにお座りになって。今すぐコーヒーを持って参りますから」リタはストンプの手を取り、テーブルのところへ導いて、背もたれの高い椅子に座らせた。そして、「モメンティート」とスペイン語で待つように言って台所へ消えて行った。
ストンプは外気にさらされて硬くなっていた手でステッサン帽を激しく回した。彼が黙っていたので、俺はなにも言わなかった。そのうちに、訳を話すだろうと思ったからだ。
リタがコーヒーを持ってきた。そして、彼女はすぐに状況を読み取り、何かがストンプを困らせているのがわかって、俺たちを二人きりにしてくれた。
「うまいコーヒーだ」とストンプは言う。
「だから俺はここにいるんだ。おいしいコーヒーとあの美人がいるからね」と俺は言った。
「俺なら、この牧場からあまり離れないように気をつけるな」とストンプ。
「牧場ならケニガンが見てくれるよ。俺が一生かかっても彼の牛に対する知識には追いつかないからね」と俺は答えた。
「そうだろうな」とストンプは考え込む。
「ストンプ?」
保安官は俺を見る。
「セント・ジョーンズからずっとほこりにまみれながら来た訳は、リタのコーヒーを飲むためじゃないだろ」
ストンプは低い声でしゃべり始めた。喉になにかが詰まっていたかのように「ナバホ・スプリングのそばで強盗がファーゴの駅馬車を襲った」と言った。
俺はストンプが訳を話すのを待った。
「ならず者がデントンを撃ち殺した。リソデンドロンの川岸を降り始めた時に。見張りも撃った。それでも止めなかった。アルバカーキから来たセールスマンも、クラウン・キングのアリス嬢も、アパッチ砦のゲインズ少佐も。一列に並ばされて殺された。畜生」ストンプは頑丈な手で帽子をつぶしてしまった。「みんな死んだ。金目の物はすべて盗まれた。それに、金庫もなくなっていた」
「郵便物も?」
「それと二万ドル。カムストック材木工場の新しい機械の金だ」
ストンプは帽子を撫でるようにしてしわを伸ばした。「ネス、頼みがあって来た。一緒にそいつらを追ってくれないか」
***
俺は昔、ストンプ・ヘールと組んだことがあった。その時、彼はグラント・クロッシングの保安官で、俺はならず者の一歩手前だった。足が長くて葦毛の馬に乗って町に来た俺は、まだ二十歳にもなっていなかった。モアブの町から南へ流れて、水のない地域に入る前にメキシカン・ハットに泊まった。それからナバホ・スプリングへ。喉にほこりが溜まっていたので、ライウイスキーで流そうという気分だった。その町にはバークレイズ酒場しかなかったので仕方なくそこに入ってしまった。
俺は上質のウイスキーのターレィズ・ミールを瓶ごとと薄汚いグラスを持って隅のテーブルに座り込んだ。ぐいっと一杯飲んだところでファーレィー・ドッドがドアを押し開けて3人の子分とともに酒場に入って来た。噂だとドッドは厄介な男だが、俺には本当かどうかわからん。とはいえ、ドッドは向こう見ずで3人の子分は部屋に散って彼の周りを見張っていた。
ドッドは部屋の真ん中に立ってバーの方を向いた。そして「シグよ、おまえは、南端に立った方がいい」とバーテンに一言。
シグは慌ててバーの端に移動した。
ドッドは子分たちに言った。「前におまえたちに言っただろ。銃を早く抜いても、狙い通りに的を撃たないと意味がないんだ。見ていろ」ドッドは片手で素早くガンベルトから拳銃を抜く。それと同時に銃の撃鉄を親指で引き、狙いを定めるや否や、引き金を引いた。するとバーの後ろに並べてあった酒瓶の中の一つが砕け散った。ドッドは拳銃をウエストベルトに戻し、再び同じ事をした。隣の瓶が壊れた。もう一度やった。そしてもう一度。
ドッドについて来た男たちは彼に目を向けなかった。彼らはドアを見張っていて、銃のハンドルに手を置いていた。俺はテーブルの下で彼らの目につかないように密かに自分の44口径を抜いて膝の上に置いた。ドッドのコルト銃が鳴り響いて、瓶が壊れた。すると、外の板張りの歩道を歩くブーツの音がした。ドッドの顔に硬い笑みが浮かぶ。男たちは面倒が起きるのを期待しているかのように、ベルトから銃を半抜きにしてはまた戻す。
足音が酒場の前を通り去る。
ドッドはまた一つ瓶を壊した。
その時、後ろのドアからストンプ・ヘールが部屋に入ってきた。「ドッド、もういいだろ」声は低かったが険があった。そして、ストンプの手にはグリーナーの散弾銃があった。
俺は自分の44口径をテーブルに置き、撃鉄を引いた。そして「俺は保安官の側だ」と言いながら、隅に立っていた男に銃を向けた。ストンプの散弾銃は床に向けられ、拳銃は右腰の後ろのホルスターに突っ込んであった。彼は一瞬俺に目を向けて首をたてに小さく振った。俺がいるのを認めたというように。
ストンプはドッドに「行くぞ」と言った。男たちを頭で指して、「連中は役に立たないよ。この坊やが銃で彼らを抑えている。こんなに物を壊しやがって。しばらく牢屋に入れてやるから。来い」
ドッドは驚きの顔で「金は払うよ。いつもそうしているから」と言った。
「ドッド、やりすぎだ。来い」ストンプは銃を渡せと言わんばかりに手を差し出した。俺は男たちを見張って、隅にいる色の黒い奴に銃を向け続けた。
ファーレィー・ドッドは、町保安官事務所の裏にある牢屋に十日間居た。そしてストンプ・ヘールは、俺に保安官助手をやらないかと尋ねた。「一日50セントで寝床と食事を出す。カウボーイの方がもうかるだろうが、おまえのやり方が気に入った」と。俺は助手のバッジをストンプから受け取り一年近く着けた。そしてその間、この真っ直ぐな男から学んだことは、俺をならず者の道から救った。
***
ストンプはコーヒーをごくりと飲み込んだ。「ネス、おまえは数多い助手の中でもずば抜けていたよ。今回は、並みの助手じゃ務まらない。駅馬車に乗っていた人たちを皆殺しにして金を盗んだ連中はほってはおけない。誓って許せねえ。一緒に行くか」
俺は「行く」と答えた。
ストンプは、俺にバッジをくれた。盾形のなかに星があって、連邦保安官助手(DEPUTY U.S. MARSHAL)と型押ししてあった。「俺がグラント・クロシングの保安官だった時から何年もたったが、奴らは駅馬車の金庫を盗んだんだから連邦犯罪だ。だから、俺の管轄だ。捕まるまで追っていくさ」と言った。
グラント・クロシングの町保安官の後、ストンプはアパッチ郡の保安官になった。だが、次の選挙でC.P.オウエンズに負けた。ところが約二週間後、ストンプは連邦保安官になっていた。そのバッジをストンプに着けたのはJ.T.カーだという噂を耳にした。俺は「ストンプ、ならず者たちをどのぐらい追う気なんだ?」と聞いた。
「一日か。一週間か。いや、一年になるか。捕まえるまで追っていくよ」
「ここに座っていてくれ。コーヒーをもう一杯飲んで。俺の支度が済んだら行こう」
ストンプはうなずいた。テーブルについたまま空のコーヒーコップを見つめていた。
台所を通った時、俺はリタに「頼む。ストンプにコーヒーを注いでやってくれ。それと、スナッフィ・デーガンに五日分の食い物を用意するように言ってくれ、それに毛布とスリッカーも。俺はケネガンにひとこと言ってくる」と言った。
リタのスパニッシュ・アイズは「分かっているわよ」と言わんばかりだった。そして、ひとことも文句を言わなかった。
ケネガン•ゼインは子牛の囲いにいた。母牛を亡くした生まれたばかりの子牛が、子を亡くした別の雌牛になつくようにしていた。なじめば人間の手で育てなくても済むからだ。
俺は「ヘレフォード牛はよく育っているな」と言った。
彼はうなずいたが目を子牛から離さなかった。
「ストンプ・ヘールが来て、ちょっと一緒に来てくれって。俺のいない間、牧場を任せるよ」
彼はまたうなずいた。
「少し時間がかかるかもしれない。」
「ネス、留守の間は俺が牧場を守るよ。絶対に」
「わかっている。感謝しているよ、ケネガン。リタに実家へ帰るかどうか聞いてみるけど、多分ここにいると言うだろう。そういう女だから」
「だろうね。でも、それは問題ない、ネス。彼女は仕事をよくするし、スナッフィの料理に太刀打ちできるからね」
俺は家に戻ろうとした。
「ボス?」
「何だ」
「俺はあんたが強じんな男だとわかっているし、その44口径を使う腕が人並み外れていることも知っている。けど、十分に気をつけてくれ。ヘール保安官が追っている奴らは縛り首になりたくないから必死に戦うはずだ。あんたの奥さんの言葉を借りれば「クイダルセ」だ。注意してくれよ」
笑みが浮かんできた。「確かに。気をつける。ありがとうよ、ケネガン」
彼はすでに馬小屋の外へと歩いていた。ケネガンのようなアリゾナ一の牧場主任がいるのは幸いだった。兄ガレッツのエイチクロス牧場のダン•トラバースにも負けないほどだ。
太陽が上らないうちにストンプと二人で牧場を出た。俺は頑丈な焦げ茶色の馬に乗り、ストンプは三色まだら馬を使った。毛布に食料を五日分くるんで鞍の後ろに縛っておいた。サドルバッグには44口径の弾を二箱と予備のコルトがあった。「あのまだら馬に乗ってならず者に密かに忍び寄ることは考えていないようだね」と俺はストンプに言った。
彼は知らん顔をした。「俺は馬の足跡から連中は5人と見ている。一人は血を垂らしていた。南へ向かったはずだ。俺の考えだと連中はモギヨンの町へ行くと思う。そこからコロラド小道でメキシコへ。俺はそう見ている」
「モギヨンへ行くなら、リトル・コロラド川の向こう側を渡って行った方が楽だ。早いのなら、分水嶺を超えてフリスコを通っていくんだね」
「今は早く行くことは重要じゃない。回って行こう。その方が馬も楽だ」とストンプは言う。
そこでエスクディーヤ山方向へ進路を取った。セブンマイルを過ぎて川幅が狭くなった所で渡った。高原へ上ってブルー山脈を避けてエスクディヤ山の丘陵地帯に出た。できる時には、馬に駈歩をさせて時間を稼いだ。坂道では馬をゆっくり歩かせながら、俺たちはしゃべっていた。まあ、俺が一方的にしゃべって、ストンプは考え込んでいたが。
「駅馬車をやった奴らは南へ向かったと見ているんだね。血を流していた奴はどのくらいの傷かな?」エスクディーヤ山から降りる途中、モギヨンの町は暖炉の煙に覆われてはっきりと見えなかった。風に乗って木煙の香りが漂い、思い込みだったかもしれないが何か濃いコーヒーの泥臭い匂いがしたような気がした。
町を見下ろす丘にストンプは馬を止めた。「そう思うね。血痕はそれほど多くはなかったが、傷を負ったのは確かだ」
「5人で間違いないか?」
俺を見たストンプの顔は苦しそうだった。「ネス、牧場では言えなかったんだが俺は追っている連中が誰だか知っている。タイ・シンクレアにキッド・マギー、それとフレンチ・デステーンとブリードと言われている男。そして、俺の息子のネイト・ヘールだ」
俺にもチェロキーの血が流れているから、ブリードという混血野郎を意味する言葉は耳触りだったが、もしストンプが、保安官として法を守ってきたことに悔いを感じているとすれば、それは息子のネイトの有様だ。ストンプはあまり家にいなかったので、優しい母のマルタだけがネイトに善悪を教える羽目になった。息子は母親が好きで父親が嫌いだった。そしてストンプは、ほとんど家にはいなかったから、息子に自由を与えすぎたのかもしれない。今では奥さんのマルタは亡くなり、息子のネイトは暴力に走っていた。
俺は深く息を吸った。「ネイトか。別に驚きはしないね。奴は小さい時から自分でトラブルを追ってきた気がする。そしてこの事件で放蕩の道を進みすぎた。俺はそう思う」
「捕まえなくてこなくては。他に方法がない」それからストンプは黙り込んでまだら馬でモギヨンの町へと動き出した。
町は急成長したように見えた。メインストリートはミネラル川沿いに北から南へと流れていた。町はずれに新しい看板があった。「ようこそアルマへ」と書いてあった。俺はストンプを見た。「モギオンはいつからアルマになったんだろう?」
ストンプは肩をすくめるようにしながら、まだら馬で、だんだん暗くなる夕暮れの中、メインストリートを下っていった。ピアノの音がかすかに聞こえてきた。行く方向に酒場がある証拠だった。交差点では窓から灯りがあふれていた。ロード・アイランド・レッドという鶏の形をした看板はまるで弁護士事務所のようだ。そこには「レッド・ヘン食堂」と書いてあった。その食堂からはとてもおいしそうな匂いが漂ってきた。思わず笑みがこぼれた。俺は「ダン、止まるんだ」と声に出して愛馬を止めた。そしてストンプに「コーヒーを一杯飲もう。それにうまいアップルパイも」と言った。
高地では日が暮れると急速に冷えてくる。しかし、レッド・ヘンの中は暖かかかった。天井から吊られたワゴン•ホイールに灯油ランプがあって隅まで明るかった。テーブルは八卓あって、それぞれに椅子は四脚。空いていたテーブルは一卓のみ。他にはカウボーイが二人と牧場主が一人、鉱山労働者、そしておしゃれをした女性がひとり。その空いている一卓に俺とストンプは座った。俺好みの隅の席ではなかったが、仕方がなかった。
台所から女の子が皿を左腕に抱えて出てきた。皿にはローストビーフとポテトとグレービーソース。右手には大きなコーヒーポットを持っていた。その子を見送る中年の女は「スミスソン先生のお宅にそれを届けたらすぐに帰っておいで。忙しいんだから。聞こえた?」と大声で言った。「ここにはこんなにたくさんのお客さんが待っているんだから」と。
ストンプと俺は目を合わせた。「ストンプ。俺のアップルパイを注文しておいてくれないか。タバコを鞍のサドルバッグの中に置き忘れた」実は俺はタバコを吸わないが、ああ言えば女の子の行方が見られる。彼女がとても上手に皿を抱えて周囲に柵のある白い家に入っていくのを遠くから見た。彼女がレッド・ヘンに戻った時、俺は元通りに座っていた。
「コーヒーのお代わりは?」コーヒーポットを持って女の子が俺たちのテーブルのそばに立つ。
ストンプはカップを差し出した。「町に新しい名前が付いたようだな」と言った。
「バーネイ中佐が町の余った土地をほとんど買ってしまいましたわ。そして町の名前をアルマに変えました。お母さんを記念しているのだそうです」
「いいことだ」とストンプは言う。「最終的に人には家族しか残らんからね。コーヒーをありがとう」
次第に他の客は食べ終わって出て行った。ストンプは肩を丸めてコーヒーをすすった。そして静かな声で「医者のところへ行こう」と言い、テーブルに1ドル銀貨を叩き付けて、いすを後ろにずらした。「行けばなにかわかるかも知れん」
女の子が片付けに来た。俺は帽子を取って「お嬢さん、俺はネス・ハヴェロックって言うんだ。セント・ジョーンズから来た。パイは本当にうまかった」と礼を言った。
彼女はエクボで微笑む。「パイを作るのはルービよ。彼女に言っておきますから」
ドアの方でストンプが声を上げた。「お〜い。ネス、早く来いよ」
俺はもう一度礼を言ってストンプの後について外へ出た。太陽はとっくにエスクディーヤ山の向こうに沈んでしまっていたが、アルマのメインストリートは馬車でごった返していた。南への三軒目は酒場で、その前のつなぎ柱に六頭ほどの馬がつないであった。さっきよりピアノの音は大きかった。ストンプは帽子をどっしりとかぶり「医者の家はどこだ?」と言った。
「あっちだ」俺は板張りの歩道から降りてほこりだらけのニューメキシコの道を歩き出した。ストンプは横にいた。俺は医者の家の門の所で止まった。ストンプは保安官。彼が先に行くべきだ。窓の左横の小さな表札にはウォルター・スミスソン医師とある。ストンプはドアをノックした。
ドアを開けた男はストンプや俺よりも背が高かった。グレーの目には生真面目な光があった。そして「どんなご用でしょうか?」と尋ねた。
ストンプはバッジを見せた。「連邦保安官のヘールだ。ナバホ・スプリングスの近くでファーゴの駅馬車が襲われた。みんな殺された。それをやった連中を追っている。残っていた血痕から一人は負傷したと見ている。ところで、お宅には患者がいるようだ。先生の許しがあれば、そいつとちょっと話がしたいんだ」
「どうぞお入りください」と言いながら医者は部屋に招き入れた。「静かにしてください。隣の寝室の若者は腹膜炎でもうじき死にます。腹部に銃弾を受けていまして…」
医者は首を横に振りながら「鎮痛剤としてアヘンチンキを使用しました。痛みが和らいで眠れるようになるので」と言った。
「そいつの名前を知っているか?」
「ここに連れてきた仲間たちはキッドと呼んでいました」
「キッド・マギーだ」
医者は肩をすくめた。
「のぞいてもいいかい?」とストンプは聞く。
医者は寝室へ先に行く。「こちらへ」とドアを開けて「短くお願いしますよ」と言った。
大きい割にストンプは静かに歩ける男だった。密かにベッドのそばまで忍んでいき寝ている男の顔を見つめた。そして少し見てからうなずいて寝室を出た。「キッド・マギーに間違いない。あとどのぐらいもつかね?」
「はっきりとはわかりません。一日?一週間?正確な判断は難しいです」
俺は一つ質問した。「好奇心から聞いてもいいかな?あの男はどう見ても食事はできない。けれど、レッド・ヘンから二人分の食事が届けられたのはなぜだ?」
医者の顔に笑みが浮かんだ。「毎日のことです。妻はよい看護婦ですが、料理が得意とは言えないのです。ですから私たちはレッド・ヘンのおいしい食事を好むのです。なぜそんなことをお聞きになるのでしょうか」
「いや。ちょっと」と俺は申し訳なさそうな顔を作った。
そこでストンプは会話を本題に戻した。「一つ教えてくれ。そいつの仲間はどこへ行くと言っていたかね?」
医者は首を横に振った。「そういう事は聞きませんでした。ただ、仲間の一人は、背の高い男で髪の毛は黒に近い色で、少しカールをしていたと記憶しています。その男は20ドル金貨を二枚くれました。そして「キッドの面倒をしっかり見な、ドック。俺はそいつとキングズ・パレスで一杯飲む約束をしたんだからな」と言いました。それしか聞いておりません」
医者はドアまで見送ってくれた。
外でストンプは帽子をしっかりと頭に乗せた。「ドック。ありがとう。邪魔したな」
「おやすみなさい」と医者は答えた。
ストンプは黙って歩き出した。しばらくするとしゃべりだした。「髪がカールしているのはネイトに間違いない。あいつはダチの面倒をよく見る奴だ」と独り言のように言った。
「ストンプ?」
「さあ、コロラド道へ行くか」
「ストンプ?」
「なんだよ」
「キングズ・パレスってわかるか?」
「知らん。で?」
「エル・パソにあるキング・フィッシャーの酒場だよ。俺が思うに、奴らはマルパイスのバッドランドを渡って行くだろう。メキシコへの近道だから」
ストンプはため息をついた。「ネス、ぐずぐずしてはいられない。すぐに出るぞ」
連邦政府の手形を使って貸し馬屋で馬を二頭借りた。一頭は足長の鹿毛色でもう一頭はがっちりしたぶち赤毛の馬だった。借りた馬に鞍を移して自分たちの馬に楽ができるようにして、俺たちはレッド・ヘンで夕食も食べずに南の荒れ地に向かった。
なんと言っても、荒れ地を通るのは危なっかしい。どこを探せばいいのか知っていれば水はあるが、馬が道を踏み外したら溶岩バッブルに飲み込まれることだってあり得る。この時は月が出ていたから小道が見えていた。できる所では馬を走らせ、できない所では軽駆けさせた。ストンプはネイトと仲間がエル・パソに着く前に追いつくことに集中していた。
夜が明けたら馬を止めて鞍を移した。俺のは焦げ茶馬に、ストンプのはまだら馬に。それから小さなたき火でコーヒーを入れ、手早く飲んで、残りかすで火を消した。
昼下がりに、連中の最初の間違いをみつけた。小道に溶岩ドームが重なっていて、そのドームの中に大きな穴が開いていた。馬を止めて、替え馬の引き綱を鞍につないだままで降りた。ドームの上を歩くのは危険なので四つんばいで進んだ。穴に近寄って、腹ばいになってのぞいた。
「ストンプ、馬が一頭死んでいる。落ちてけがをしたようだ。連中は、こいつを撃つしかなかったんだろう」と言った。
俺は馬のところに戻って縄を拾った。替え馬をつないだままで鞍を下ろした。溶岩の厚そうな淵を選んで、鞍の敷布をかけて、縄が切れないようにした。そしてもやい結びで自分に縄を着けた。
ストンプに縄の端を渡した。「ゆっくり下ろしてくれ。死んだ馬を調べるから」
溶岩ドームの中に入ると、馬の前足が折れていて、横腹には深い傷があった。触ってみると冷たくなっていた。前足をつかんだら膝で曲がった。横壁まで行ってストンプを呼んだ。「上げてくれ」
ストンプが引っ張り上げてくれた。
「馬は冷たいがまだ硬くなっていない。馬が一頭死ねば誰かの馬が二人を運ぶ羽目になる。それに馬が落ちた時に乗っていた奴がけがをしたかどうかもわからん」俺はストンプを見つめた。「俺たちが追っていることを奴らはわかっているんだろうか」
「遅かれ早かれ分かるさ」
「隠れて俺たちを待ち伏せるのか」
「そうするだろうよ」
「くそ」
ストンプは言う。「鞍を付けろ。行くぞ」
日暮れの溶岩の峡谷で、洞穴の中でベーコンと焼きパンをわずかなたき火で作って食べた。馬たちはノーズバッグに顔を突っ込み残りの大麦を食べていた。水は水筒の中にある分しかなかった。
「リオグランデ川はまだ遠い。途中でどこかに水はあるか?」とストンプは俺に尋ねる。
「もし探せるならあるにはある。最も近いのはイーグル・ネスト・タンクだ。ここから20マイルほどだろう」
ストンプはベーコンをパンに包んでかじった。「朝までに着くかな?」
「昼までかかるだろう。ここからイーグル・ネストまでの間は結構荒れているんだ」俺もパンとベーコンをかじった。うまかった。水を一口だけ飲んだ。
ストンプはサドルバッグの中のなにかを探していた。やがて銃弾が入っている布袋を取り出した。「ちょっと銃の練習をしてくる」と言ってたき火から離れた。俺からは見えなかったが、銃を撃って、また弾を込めて撃って、を五回繰り返した。正確に撃つためには練習しなければならない。ストンプはいつも練習していて、必要な時に正確に撃つ男だった。
ストンプは戻ると座り込んで、銃の手入れを始めた。俺に「寝ろ」と言う。「月が出てきたら起こす。そうしたら出かける」
目を閉じたと思ったら、ストンプが俺の肩を揺らした。月は渓谷の淵からでものぞけるような満月だった。借りた馬に鞍を付け、小道をたどった。そして、日の出から一時間ぐらい経ったところで銃声がしたので止まった。
ライフルの銃声とともに、ストンプは撃たれたかの如く乗っていた馬から落ちた。しかし素早く転がって隠れたので弾は当たっていないと見えた。俺は乗っていた替え馬からすっと降りながら44-40ライフル銃を鞘から抜いた。だが岩の後ろに隠れるや否や、弾はその岩の一角を砕いた。替え馬は俺の焦げ茶色の馬と一緒に、来た方向へと駈けた。ストンプの二頭もそれを追った。少し待って口笛を吹いた。運が良ければ俺の馬はその合図で止まる。
「ストンプ」
彼は俺の方を向いた。俺は自分のウインチェスターを彼に投げた。俺は「撃っている奴の注意を引いてくれ」と言って、馬の後を追った。運が向いていた。岩場のそばで俺の馬は立ち止まっていて、他の馬も近くで雑草を食っていた。ウインチェスター銃が鳴って、弾の音がキーンと峡谷の向こうへ響いた。ストンプは頼んだ通りに奴の注意を引いていた。俺はサドルバッグからモカシンを取り出し、帽子を脱いで、頭を茶色いバンダナで覆った。テキサスレンジャーを父に、チェロキーインディアンを母にインディアン領地で育った俺はインディアンが自然に溶け込む術を身につけた。ライフル銃を撃っている奴はストンプだけに目をつけているから、やがてそいつの首には俺の拳銃が押しつけられるだろう。
44口径をホルスターから取って弾と装置をチェックした。シリンダーに6個目の弾を突っ込み、ホルスターに戻して、撃鉄に革ひもをかけ、ホルスターに固定した。
そこで俺は白人の世界からインディアンの世界に戻った。丘を上った。下の方でスタンプは適当にライフルを撃っていて、待ち伏せした奴の注意を引いていた。そいつから400メートルぐらい離れた所で俺は淵を上りきった。それから淵に沿って猫のように音を立てずに近づいて行った。もちろん、十分下がって俺の輪郭がわからないように気をつけた。
岩に囲まれている所で男を見つけた。モカシンを履いているので忍び寄ることができた。最後の数メートルは30分ぐらいかけて近づいて、やっと手を伸ばせば触れるほどになった。
俺は「銃を置いて手を上げろ」と言いながら拳銃の撃鉄を引いた。奴は固まった。銃口を首に突けてブスカデロ風のホルスターから奴の拳銃を抜いた。そして「おまえはもう終わりだ。ライフルを捨てろ」と言った。
男はライフル銃を離した。俺はそれを拾って声を上げた。「ストンプ!降りて来いよ」コルト銃で奴を突いた。「首の後ろに手を組め。保安官と話しに行くぞ」
男はフレンチ・デステーンだった。そいつを替え馬に縛り付けて残った三人を追って馬を走らせた。フレンチは仲間が必ず待ち伏せているに違いないと言った。自分たちは自由にメキシコへ逃げられると。「おめえら二人を殺るのはどうっちゅうことはない」と言う。「駅馬車の奴らもみんな殺ったし、金も取った。すげえ量の金だぜ」フレンチは盛んに自慢話をする。
ストンプは先頭のまだら馬に乗って、栗色馬を引っ張っていた。ストンプらしく鞍に真っすぐに座っていた。ストンプの後ろに俺、そしてフレンチが最後。奴は縛り首になるのを認めたくはなかったようだ。
気を張って進んだ。ライフルを手に、目で周りを細かく見回した。スクラブ樫とピニョン松は石と石の間でやっと生きていた。渓谷の淵の上に、空に羽を伸ばしていた紅尾鷹が一羽。普通ならその美しい風景に見とれるはずだが、今は銃弾がいつどこから跳んで来るかと気を張るしかなかった。
銃弾が飛んできた時、ストンプのまだら馬の先の小道でほこりを立てて銃声がした。撃った奴の位置は銃煙で標された。俺は栗色馬の反対側から降りた。良い馬だったが俺よりも馬に弾が当たるようにしたかった。ストンプはライフル銃を手にしたまま動かなかった。
「親父?」
「聞こえている、ネイト。ライフルを下ろして出てこい。俺を捕まえに行かせるな」
「親父。あんたには何も出来ないよ。俺は狙い撃ちだってできる。死にたくなきゃフレンチを離して、銃を捨てろ。今すぐに。それから後ろに下がれ」
フレンチがあざ笑った。「爺さんよ。だれがボスだと思っているんだ。バカたれ」
「親父!聞こえないのか?銃を捨てろ!」
ストンプはため息をつき、ライフルを小道の脇へ投げ捨てた。そして「ネス」と言った。その意味はわかっていた。俺もライフルとコルトを彼の銃のそばへ投げた。
「フレンチの銃も」とネイトは声を上げた。ストンプはその銃も投げた。
「よし。引き下がれ」
ストンプはまだら馬を下げさせた。俺は自分の馬を引っ張って歩き、捨てた銃が見える所で止まった。
フレンチは大声を上げた。「お〜い、ネイト。この鞍に縛られてるんだよ」
ストンプはまだら馬から降りた。そして「ネス、サドルバッグにあるコルトをくれ」とささやいた。
「ストンプ、あっちには四人いるぜ。あんたは一人だし」と俺。
「俺の息子は、俺の責任だ。拳銃をくれ!」
俺はストンプに44口径を渡した。
彼は手を出した。「銃弾!」
俺は弾の箱を開けて、弾を鷲づかみにして渡した。
ならず者たちは歩いて銃を取りに来たから、馬は比較的遠い所につないでいたようだった。奴らは高笑いをしながら銃を拾った。その時は、奴らにとって世界はバラ色だったに違いない。ストンプは俺の44口径のコルトに弾を込めた。そして手を下げて銃を足の脇に持ちながら、ならず者の方へ歩き出した。ネイトと仲間はストンプの動きには気づかないようだった。
ストンプは大声で「ナサニエル・ヘール!銃を捨てて降参しろ。おまえは間違ったことをしたんだ。だからそのツケを払わなきゃならない」と叫んだ。
肌の黒いブリードと呼ばれる男が素早く撃った。弾はストンプの3メートルも前でほこりを立てた。ストンプは冷静に拳銃を上げ、狙いを定め、そして体重が右足に乗った所で引き金を引いた。ブリードは腕を広げて糸が切れた操り人形のようにつぶれた。
フレンチの銃はまだストンプが投げたままだった。ストンプはそれを拾うためにダイブした。ネイトとタイ・シンクレアが同時に撃ったが拳銃で動く標的に当てるのは難しい。相当練習しないとできないことだ。
ストンプは真っすぐに歩き続けながら言った。「ネイト、おまえを撃ちたくないが…」
ネイトは笑ってもう一発撃った。
ストンプはよろめいたが、また歩き出した。拳銃を上げて狙いを定めた。また右足に体重がかかった時に撃った。弾はフレンチの15センチほど前の小道の硬い地面から跳ねて彼の額を荒く削った。フレンチは崩れて動かなかった。ストンプは歩き続けたが左脇から血が滲み出ていた。
シンクレアが撃った。ネイトも撃った。ストンプは倒れたが、反射的に44口径を撃つと、シンクレアは屠殺された牛のように崩れた。
ストンプは何とか立ち上がり、「ネイト、銃を離せ」と言った。
ネイトは首を横に振った。「親父、それは出来ん。俺を連れて帰らせるわけにはいかねえ」そしてネイトは拳銃の撃鉄を引いて真正面からストンプを撃った。
ストンプは小道に大の字になって倒れた。
ネイトはゆっくりとストンプに近づいて父親の顔を眺めるようにした。「俺が何をしても親父は認めてはくれなかった。だから何もできなかったよ」
ストンプの大きな左手が動き、上がった、そしてネイトのジーンズをつかんだ。「やめろ」と小さな声。「今すぐやめろ。さもないと一生逃げ回ることになるぞ」
「親父。あんたはなにも分かってないんだ。あんたはもう死でるんだよ」と言いながらストンプの手を振り払った。
ストンプの右手にあった拳銃は自分の意思で上がったように見えた。上向きになった拳銃はネイトの身体に弾を撃ち込んだ。そして小道に落ちた。
「くそー…」ネイトはゆっくりひざまずくようにストンプの足の上に倒れた。
俺はストンプと彼の息子の遺体をグラント・クロッシングまで運んだ。そして二人の母であり妻であるマーサのそばに眠らせた。セント・ジョーンズでオーエンズ保安官にコムストックの金を預けたが、連邦保安官のバッジは取っておいた。ストンプを埋葬してから二週間ほど経った時、M.K.ミード連邦保安官がRP牧場を訪ねてきた。
コーヒーを飲みながらミード保安官は「ストンプ・ヘールとその息子の話を聞いた」と言った。
「残念ながら、俺には見届けることしかできなかったが」
「ハヴェロック、ストンプはいい保安官だった。彼の口癖は、正しいことをしようとする男はどんな妨げも乗り越えることができる、だったな」
俺は隅にある机からストンプと俺が着けていたバッジを取り出した。「ミード保安官」二つのバッジを手の平に乗せて差し出した。「これをお返しします」
保安官はバッジを受け取って、補佐のバッジをポケットに入れた。だが連邦保安官のバッジは手の平に乗せたままだった。「ネス、この国は成長している。だから、正しいことをしようとする男が必要なんだ。どうだろう?ストンプを喜ばすためにも、このバッジをつけないか?アリゾナの北部には有能な保安官が必要だ。俺はおまえが適任だとにらんでいるが、やってくれるか?」
妻のリタがドーナツを山盛りにした皿を持って部屋に入ってきた。「ミード保安官、俺たちのコックのスナッフェイはアパッチ郡で一番うまいドーナツを作るんです。食べてみませんか」
そして保安官の微笑みは十分な答えだった。
俺はリタに「ミード保安官が、俺にストンプのバッジをつけろと言っているがどう思う?」と聞いた。
すると彼女は、俺の目を見つめながらこう言った。「ジョハネス・ハヴェロック、いつもと同じように、あなたはきっと正しい選択をなさるでしょう」と。
完
Chuck Tyrell署
(日本語訳推敲 田中雄二・晶子)
Thursday, July 8, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)