私にもチェロキーの血が流れていて、ブリードと混血野郎と意味をする言葉は耳触りだったが、もしストンプは保安官で法を守って来た年々に悔いを感じていたならばそれは息子ネイトの有様だ。ストンプはあまり家にいなかったので優しいお母さんのマルタだけが彼に善悪を教えるハメになっていた。息子はお母さんが好きでお父さんが嫌いだった。そしてストンプ、ほとんどいなかったから、息子に余裕を与えすぎたかもわからない。今では奥さんのマルタは死去でネイトは暴力に走っていた。
深く息を吸った。「ネイトか。なんだか驚きにいたらないね。小さい時からトラブルを追って来た気がする。この事件で道楽への道を進み過ぎた。俺はそう思う。」
「捕まえて来なくちゃ。他に方法がねえ。」それでストンプは黙り込んでまだら馬をモギヨン町へと動き出した。
町は急成長したように見えた。メインストリートはミネラル川添えして北から南へと流れた。町はずれに新しい看板があった。「アルマへようこそ」と書いてあった。ストンプの顔を見た。「モギオンはいつアルマになったんだろう?」
ストンプは肩をすくめるようにして、まだら馬をだんだん暗くなりつつの夕暮れのなかでメーンストリートをくだっていった。ピアノの音はかすかに聞こえて来て、行く方向には酒場がある証拠だった。交差点で窓から灯りが溢れた。ロード・アイランド・レッドという鶏の姿をしていた看板はまるで弁護士事務所のようだった。「レッド・ヘン−食事所」ってかいてあった。またその食事所からはとても美味しそうな匂いが漂ってきた。思わず笑みがでた。「焦げ茶の馬よ。とまれ」って声をだして愛馬を止めた。ストンプに「コーヒー一杯のもうぜ。それにうまいアップルパイも。」
高知では日が暮れると速に冷えてくる。しかし、レッド・ヘンの中はあったかかった。天井から吊ってあったワゴン•ホイールに灯油ランプがあって隅まであかるかった。テーブルは八卓あって、それぞれに椅子は四脚。開いていたテーブルは一卓のみ。他にはカウボイ二人と牧場主一人、鉱山労働者、そしておしゃれをしていた女性ひとり。その開いている一卓に私とストンプは座った。私好みの隅のではなかったが、しかたがなかった。
台所から女の子が皿二を左腕に抱えって出て来た。皿にはローストビーフとポテートとグレービソース。右手に大きなコーヒーポットを持ってました。その子を見送る中年の女は「スミスソン先生のお家にそれを届けたら早速に帰ってこいよ。磯がしんだから。聞こえる?」と大声で言った。「ここにこんなにお客さんが待っているんだから」と。
ストンプと私は目を会わせた。「ストンプよ。俺のアップルパイを注文してくれ。俺、タバコを鞍のサドルバッグの中に置き忘れた。」実はタバコを吸わないがああいえば女の子の行方を見れた。遠くから彼女がとても上手に皿を抱えて小回りな白い家に入っていったのを見た。彼女はレッド・ヘンにもどったら、私は元通りに座っていた。
「コーヒーのお変わりは?」コーヒーポットを持って女の子が私たちのテーブルの側に立つ。
ストンプはコップを差し出した。「町に新しい名前が付いたようだな」と言った。
「バーネイ中佐が町の余った土地を殆ど全部かってしまいましたわ。町の名前をアルマに買えました。お母さんをp記念しているそうです。」
「いいことだ」とストンプは言う。「最終的に人には家族しか残らんからね。コーヒーありがとうよ。」
次第に他の客は食べ終わって出て行く。ストンプは肩を丸めてコーヒーをすすった。静かな声で「よ、医者のとこいかんか。」テーブルにドル貨を叩き付けて、椅子を後ろにずらした。「行けば何か分かるかも知れん。」
女の子が片付けに来た。脱帽して「お嬢さん。俺、ネス・ハベロックって言うんだ。サイント・ジョンズ方向から来たものだ。パイは本当にうまかった。」
彼女はエクボで微笑む。「パイを作るのはルービよ。言っておきますから。」
ドアの方でストンプは声を上げた。「おおい。ネスよ。来い。」
も一回脱帽をしてストンプの後に外へいった。太陽はとっくにエスクディーヤ山の向こうで沈んでしまっていたが、アルマのメーン•ストリートは馬車で忙しくしていた。南への三件目は酒場でその前のつなぎ柱に六頭ほど馬が繋いであった。先よりピアノの音は大きかった。ストンプは帽子をどっしりとかぶった。「医者の所は何処だ?」と。
「あっち。」私は板張り歩道からおりてほこりだらけのニューミキシコの道に歩き出した。ストンプは横にいた。医者の家の杭垣にある門の所で待った。ストンプは保安官。彼は先に行くべきだ。窓の左横に小さな表示にウオルター・スミスソン医師と表してあった。ストンプはドアにノックした。
ドアを開けた男はストンプと私より背があった。グレーの目はきまじめな光があった。「紳士のお二人、何か私で出来る事があって?」と尋ねた。
ストンプはバッジを見せた。「ヘールと言うんだ。連邦保安官で。ナバホ泉の近くにファーゴの駅馬車は襲われた。皆射殺で死んだ。それをやった連中を追ってるんだ。残った血滴で一人は負傷したと見ている。それにお宅の所に間借り人がいるようだ。先生の許しがあったら、そいつにちょっと話をしたいんだ。」
「お入りください、ゼントルメン。」医者は部屋に下がった。「静かにしてください。隣の寝室の若人は時期死にます。腹膜炎。腹部に銃弾を受けまして・・・」
医者は頭を横に振る。「鎮痛剤としてアベン酒を使用しました。痛みを和らいで眠れるようになるので。」
「名前を知っている?」
「仲間たち、ここに連れてきた男たち、はキッドと呼んでいました。」
「キッド・マギーだ。」
医者は肩をすくめた。
「覗いていいかい?」とストンプは聞く。
医者は寝室へと先に行く。「こちらへ」ドアを開けて「短くお願いします」と言う。
大き男のわりにストンプは静かに歩ける人だった。密かにベッドの側まで忍んで寝ている男の顔を見詰めた。一時見てから頷いて寝室をでた。「キッド・マギーに間違いない。どのぐらい持つかね?」
「はっきりと分かりません。一日?一週間?この病気は読みにくいです。」
私は一言を質問した。「俺の小寄進だけですが聞いてもいいだな?あそこの男はどう見ても食えないよね。けど、レッド・ヘンから二人分の食事が届かれたのはなぜだろう?」
医者の顔に笑みが浮かんだ。「毎日のことです。妻、いい子ですが、看護婦ですが料理が得意とは言いがたいのです。二人ともレッド・ヘンの美味しい食事を好むのです。なぜ聞かれるのでしょうか。」
「いやっ。ちょっと」と申し訳なさそうな顔を作った。
そこでストンプは会話を本題に戻した。「一言を教えてくれ。そいつの仲間は何処へ行くんかを言ったかね?」
医者は首を横に振った。「そのような事をききませんでしたね。仲間の一人、瀬の高い人で髪の毛は黒に近い色だった、少しカールをしていたと記憶しています。その男性は二重ドル金貨二個をくださいました。‘キッドの面倒をしかり見な、ドック。キングズ・パレースで一杯をのむって約束したんだからね。’と言いました。それしか聞いておりませんですね。」
医者はドアまで見送ってくれた。
外でストンプは帽子をしっかりと頭に乗せた。「ドックよ。ありがとう。邪魔したな。」
「おやすみなさい」と医者は答えた。
ストンプは黙って歩き出した。暫くすると喋りだした。「髪がカールしているのはネイトにまちがえねえ。だちの面倒をよく見るやつだ。」独り言のように言った。
「ストンプ?」
「さあ、コロナド道へと乗るか。」
「ストンプ?」
「なんだよ。」
「キングズ・パレースって知っている?」
「知らん。で?」
「エル・パソにあるキング・フィッシャーの酒場だよ。俺に言わせれば奴らはマルパイス荒れ地を渡っていくんだろう。メキシコへの近道だから。」
ストンプはため息をついた。「ネスよ。ゆっくりできんよ。出るよ。今!」
貸し馬屋で馬も二頭を連邦政府の手形で借りた。一頭は足長の鹿毛色でもう一頭はがっちりしたぶち赤毛の馬だった。借りた馬に鞍を移って自分たちの馬が楽にできるようにして、レッド・ヘンで夕食もたべずに南へと荒れ地に向かった。
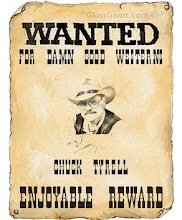
No comments:
Post a Comment